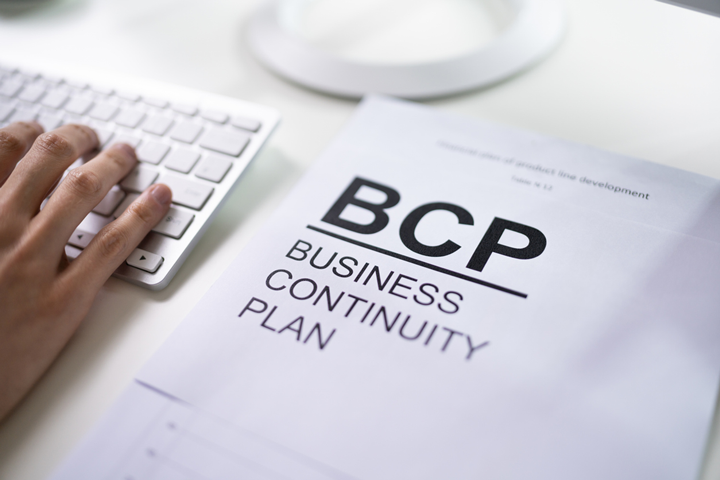目次
1. 週末を直撃したETCシステムの大規模障害
2025年4月6日の日曜日、高速道路利用が最も多くなる週末にETCシステムが突如として機能しなくなるという大規模なトラブルが発生しました。東京、神奈川、静岡、山梨、長野、愛知、三重、岐阜の8都県、あわせて106か所の料金所でETCが使えなくなったのです。復旧までに丸一日以上を要し、渋滞や料金所での混乱が全国各地に広がりました。
この障害に対し、ニュースやSNSでは現場からの中継をまじえ、「対応が遅い」「説明が不十分」といった利用者の不満の声が相次ぎました。週末の混雑時であったことも影響し、トラブルの現場の負担は相当なものだったと想像できます。私はこのニュースに触れたとき、批判の前にまず、現場で対応にあたっていた技術者や運用担当者たちのことをおもいました。
2. 原因は単純ではない--表面に見えない複雑性
今回のトラブルについて、中日本高速道路は当初、4月5日に行った深夜割引制度の見直しにともなうシステム改修が影響したと説明していましたが、7日夕方には「改修を行ったシステムとは別の部分に起因する可能性がある」と訂正しました。部分的な変更が予期せぬ連鎖を生んだ可能性があり、全体像の把握が困難なほどにシステムが複雑化していることが見て取れます。
私はこの状況を聞いて、過去にたびたび発生したみずほ銀行のシステムトラブルを思い出しました。複数のレガシーシステムを継ぎ接ぎ的に維持していた結果、誰一人として"全体を把握できる人がいなかった"という、あの構造的な問題です。今回のETC障害も、同様の「複雑さの罠」に陥っているのではないかと、同じインフラに携わる者のひとりとして感じました。
3. 私たちの誰もが直面する「全体最適」の難しさ
情報インフラの世界において、特に長く運用されているシステムでは、「一部を直すと他が壊れる」「全体像が見えない」といった問題に頻繁に直面します。どれだけ丁寧に設計していても、時代とともにパッチがあたり、別の要件が積み上がり、気づけば"誰も手をつけられないブラックボックス"と化すことも少なくありません。
そうした状況下でも、インフラの現場では日々多くの技術者たちが、目立たぬところで汗をかき、トラブルを未然に防ぐ努力を続けています。今回のように表面化してしまうケースは稀ですが、むしろ「何も起きない日常」を支えるために、多くの知恵と経験、そして責任感が注がれているのです。
4. 私自身の現場経験と重ね合わせて
私も通信インフラに携わる立場として、今回のETCトラブルは決して他人事とは思えませんでした。「なぜこんなトラブルが起きたのか?」という問いと同時に、「どれだけの人が、どれだけの緊張感をもってこの事態に向き合っていたのか?」という思いが浮かびました。
特に、週末にシステム障害が発生したという事実。おそらく、関係者は休日に呼び出され、休む間もなく復旧対応に追われていたはずです。現場で深夜まで画面を見つめ続けるエンジニア、説明責任を背負うマネージャー、怒号の中で対応にあたる作業員、そのすべての"仲間"に私は心から敬意を表したいと思います。
5. 「正常に動いて当たり前」は最大の賛辞
インフラの世界において、「正常に動いて当たり前」は最大の賛辞であり、同時に最大のプレッシャーでもあります。だからこそ、私たちは今回のような事例を単なるトラブルとして片付けるのではなく、同じ現場の一員として、自分自身の仕事に引き寄せて考えるべきだと感じています。
誰もが見ていないところで、誰かが責任を持って支えている。今回のETC障害を通じて、私はあらためてその事実を思い出しました。そして、私自身の仕事でも一つひとつの判断がシステム全体にどう影響を及ぼすかを常に意識し、より良いインフラを築くために日々精進していこうと、気を引き締めた次第です。
最後までご覧いただきありがとうございました。